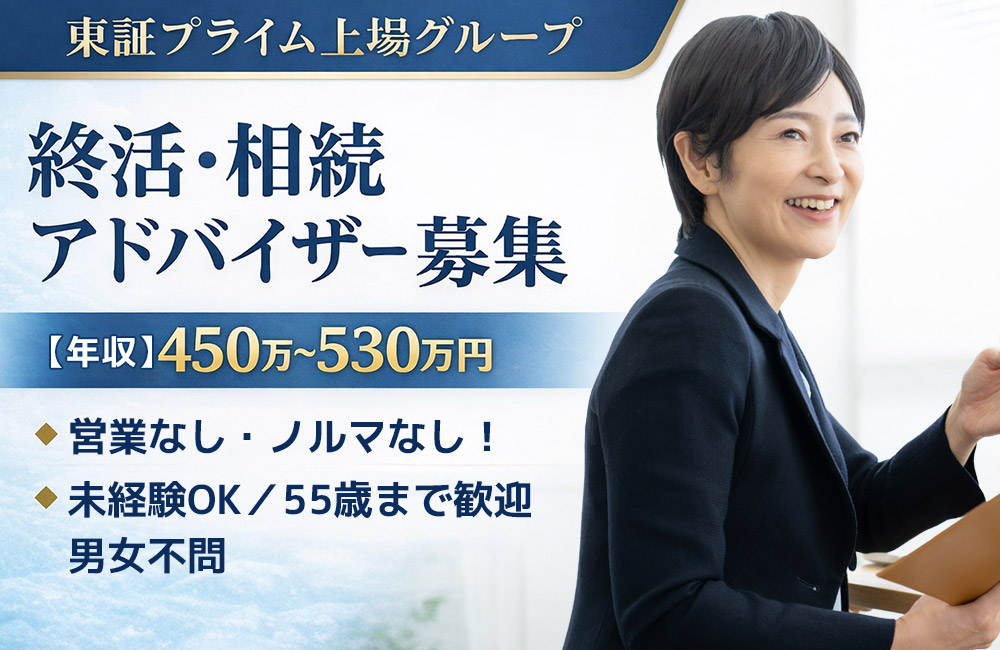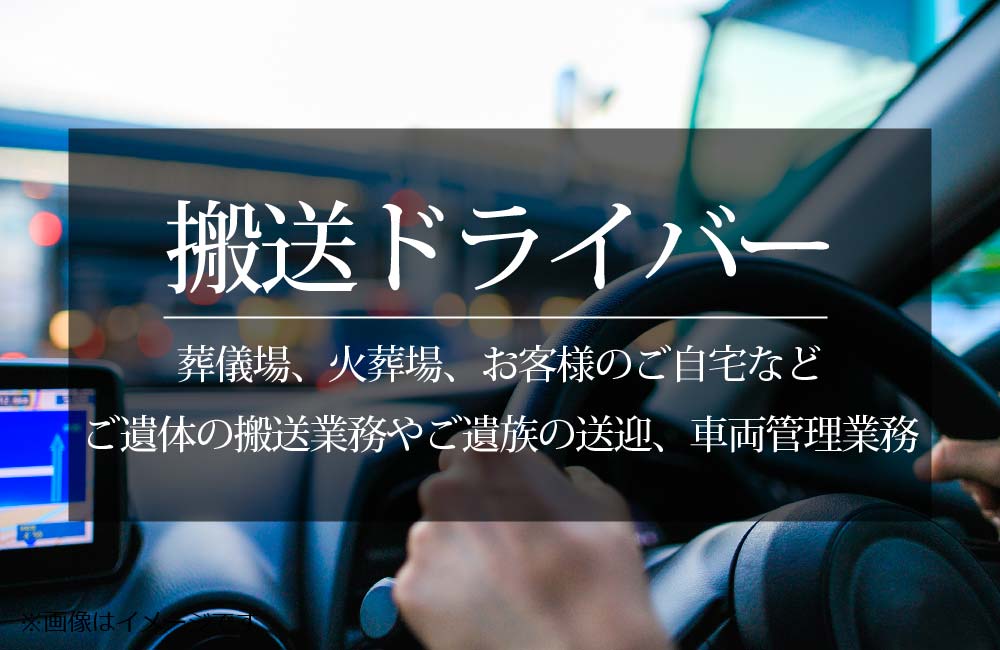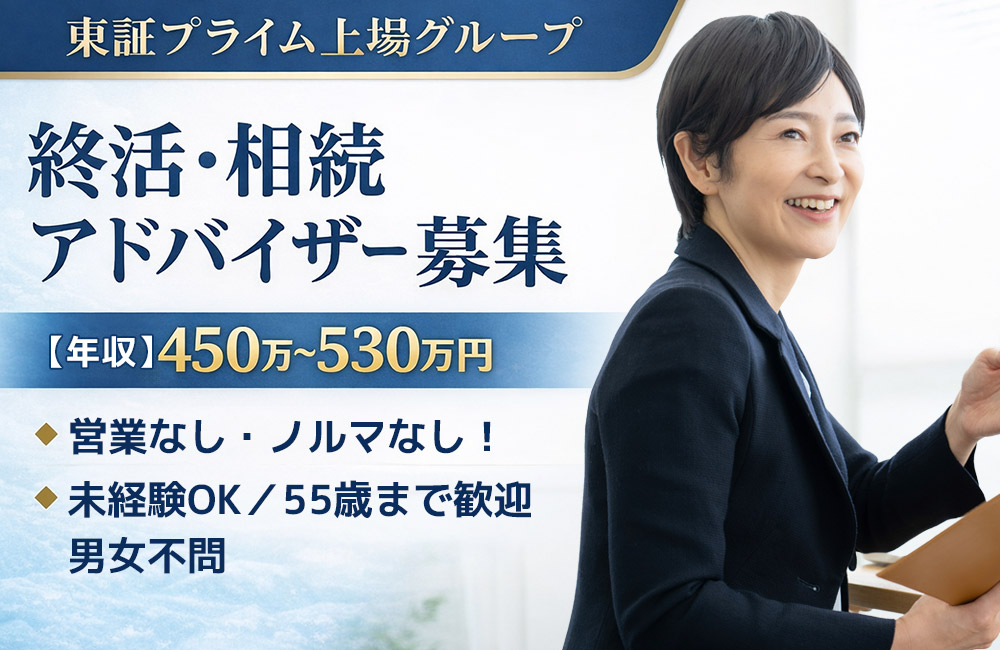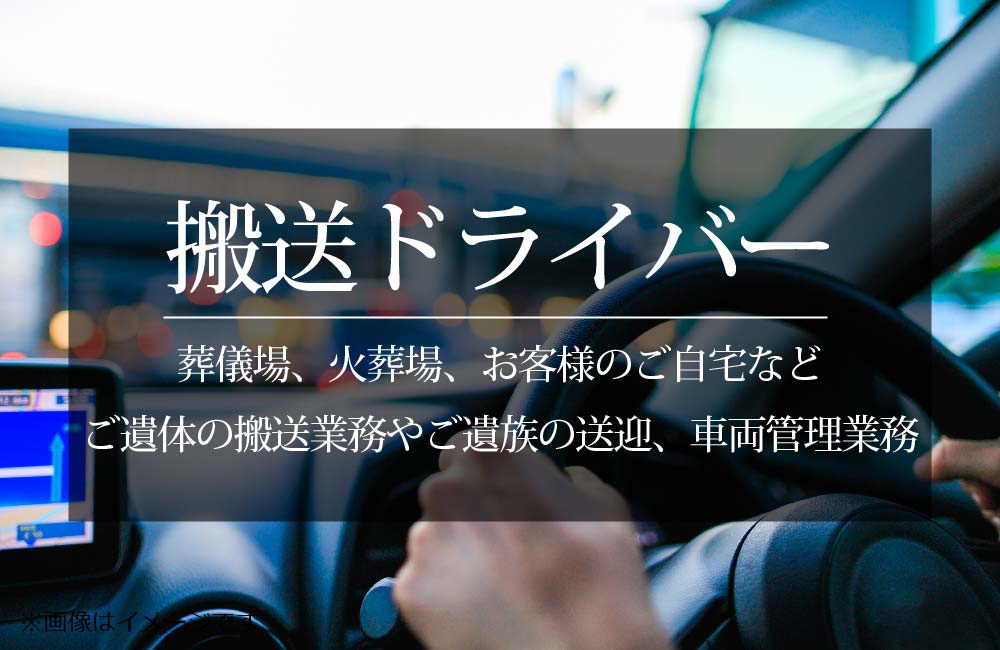今回は、業界最大手の公益社に転職をしたSさんにお話を伺いました。
前職でも葬儀業界での経験があったSさんは、より広い経験を求めて公益社へ。現在は主に家族葬を担当し、ご遺族の想いに寄り添った“まごころ”の提案に力を注いでいます。
会社の共有文化や柔軟な社風にも支えられながら、自分らしいスタイルで成長を重ねてきたSさん。経験から気付けた自分の本音や今後の目標などを語ってくださいました。
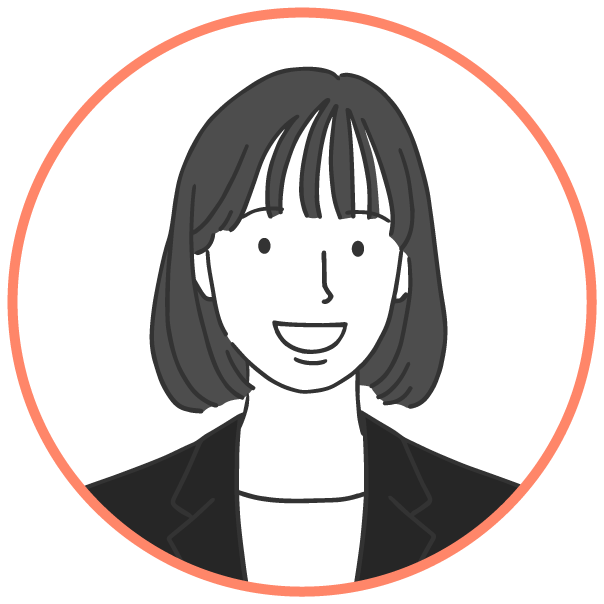
Sさんが公益社に入社されて、1年ちょっとというところでしょうか。
S:そうですね。
現在はどのようなお仕事を担当されていますか。
S:今は葬儀の担当と、事前の打ち合わせを行っています。
ということは、すでに葬祭ディレクターとして一通りの業務を任されているということですね。
S:はい、そうです。
すごいですね。ちなみに、担当デビューされたのはいつ頃だったか覚えていますか。
S:入社して半年くらいだったと思います。
それは早い方でしょうか。
S:どうなんでしょう?
私は以前も葬儀会社に勤めていた経験がありましたが、研修は通常通りしっかり受けて、その後に担当になったという流れでした。
入社から半年で担当に就かれて、そこからさらに半年以上が経つわけですが、最近印象に残ったご葬儀などはありますか。
S:公益社では「まごころ枠」という取り組みがあって、故人様が思い入れのある物をご用意したり、好きだったものを葬儀で取り入れたりできるんです。
最近では、ハーゲンダッツのラムレーズン味が好きだったという方がいらっしゃって、ご家族からそのお話を伺ったので、葬儀当日にご用意させていただきました。ご家族にもとても喜んでいただいて、棺にも一緒に入れてくださいました。
 公益社から故人様へのプレゼント”まごころ枠”担当者が工夫し用意する。
他にも、ゴルフが好きだった方がいらっしゃって。その時は先輩が「こんなことしたことがあるよ」と教えてくれて、抹茶パウダーを使ってケーキの上にゴルフ場を再現したんです。爪楊枝を使ってゴルフクラブのようなものを作ったりして、それをお渡ししました。それも棺に入れていただけて、すごく印象に残っています。
公益社から故人様へのプレゼント”まごころ枠”担当者が工夫し用意する。
他にも、ゴルフが好きだった方がいらっしゃって。その時は先輩が「こんなことしたことがあるよ」と教えてくれて、抹茶パウダーを使ってケーキの上にゴルフ場を再現したんです。爪楊枝を使ってゴルフクラブのようなものを作ったりして、それをお渡ししました。それも棺に入れていただけて、すごく印象に残っています。
ケーキでゴルフ場を再現するとは…すごいアイディアですね!
S:はい(笑)。ゴルフボールやクラブは棺に入れられないこともあるので、どうにか形にできないかと工夫しました。
そういった“まごころ枠”のアイディアは、ご遺族の方からリクエストされるわけではなく、公益社さん側からのご提案なんですか。
S:そうですね。スタッフがそれぞれ打ち合わせの中で、ご遺族からお話を伺いながら、「何かできることはないか」と考えて準備をしています。葬儀当日に担当が変わることもあるので、打ち合わせ担当者からの引き継ぎも大切です。
先ほどのゴルフのケーキのように、先輩が過去の事例を教えてくれることも多いですし、良い取り組みは共有する文化があります。
やはり、公益社はスタッフの人数も多いので、それだけ色々なアイディアが集まりやすく、さらにそれを共有する仕組みがあるのも大きいですね。
その「共有の仕組み」は、具体的にどのようなものでしょうか。
S:データベース化されていて、写真付きで「こんな故人様だったので、こういう物をご用意しました」と記録されています。
それは貴重な情報ですね。リピーターのお客様がいらっしゃった場合にも、前回の情報を踏まえてご提案ができそうですね。
S:はい。全てのケースで写真が残っているわけではないのですが、データ上に「まごころ枠」という欄があって、そこに内容が記載されていれば、ある程度はイメージができますね。
本当に“想いを届ける仕事”という印象を受けました。ありがとうございます。
S:今のところはあまり大きな葬儀は担当していなくて、基本的に家族葬が多いです。
公益社さんは大手ですから、大規模な葬儀のノウハウも豊富にあるかと思います。将来的に大きな葬儀にもチャレンジしてみたいという気持ちはありますか。
S:先輩が担当した大きな葬儀に入ったことはありますが、実際に見て「ちゃんと対応ができてすごいな」と思う反面、ご家族との距離感を大切にできる家族葬のほうが、自分には合っているかなと思っています。
以前は、もっと規模の大きな葬儀にも携わりたい気持ちが強かったのですが、今はお話をじっくり伺えたり、故人様のことを深く知れたりする家族葬に魅力を感じています。
公益社さんでは売上目標なども設定されていると思いますが、その点についてプレッシャーを感じることはありますか。
S:私は今、プランナーというより施行側なので、営業というほどではなく、金額的な部分にそこまで関わっていないんです。
ですから、正直プレッシャーはあまり感じていなくて…本当は感じなきゃいけないのかもしれませんけど。
でも、そのバランスが公益社さんらしいというか。会社からガツガツ言われるのではなく、それぞれの得意分野を生かす社風なんですね。
S:そうですね。売上やオプションの獲得率などのランキング表は共有されますが、スタッフそれぞれで受け取り方も違いますし、頑張り方も違うと思います。
エンバーミングについては、会社としても推奨している施術だと伺いました。実際にご提案される場面では、どんなお話をされているのでしょうか。
S:エンバーミングは自社の用賀会館で対応ができますので、可能な限りご提案をするようにしています。
最近は火葬までの日数が空いてしまうことも多いので、そういった場合には「ぜひエンバーミングを」とお勧めしやすいです。ただ、日程が短いと必要性を感じにくいこともあるので、そのあたりは状況を見ながら臨機応変にご提案することを心掛けています。
状況次第でご提案の仕方も柔軟に変えられているんですね。
S:はい。例えば、亡くなられた後にお口が開いてしまうこともあるのですが、エンバーミングを行うことでそれを整えることができます、というようなご説明もしますし、「亡くなってもきれいな姿を維持したい」という思いに応えるときにも、エンバーミングをお勧めします。
S:いえ、2024年の10月からは日吉会館の所属になっています。ですから日吉への出社が比較的多いですが、その日によって出社先は変わります。
用賀会館と日吉会館では、雰囲気などに違いはありますか。
S:用賀会館はスタッフがたくさんいて、皆さん忙しそうなんですよ。だからちょっと話しかけづらい雰囲気があるかもしれません(笑)。
一方で、日吉会館はアットホームな感じがあって、社歴が長い方も多いので、いろんなお話が聞けるのが良いなと思っています。
それは素敵な環境ですね。
少し話題が変わりますが、今回の転職活動は葬祭ジョブでサポートさせていただきました。当時、複数の求人をご案内した中で、最終的に公益社を選ばれた理由をお伺いしてもよろしいですか。
S:一番の理由は「大きな会社だから」という点です。前職では少人数の体制で家族葬ばかりだったので、もう少し大きな規模の葬儀も見てみたいな、という気持ちがあって決めました。
実際には、現在も家族葬が中心とのことですが(笑)
S:そうなんですよ(笑)。
でも今は先ほども話した通り、逆に「やっぱり家族葬がいいな」と思えているので、結果的に自分に合ったスタイルが見えてきた気がします。
転職して大変だったことや、葬祭ジョブへの要望などはありましたか。
S:特に大変だったことや不満はなかったですね。サポートもしっかりしていただいたと思っています。
転職前に「現場での経験を通じて提案の幅を広げたい」と話されていたかと思いますが、実際に公益社に入社してから実現できた点、また変化を感じた点はありますか。
S:働き方としては、前よりも残業時間がかなり減って、早く帰れる日が増えたというのはすごく大きいです。これは本当にありがたいですね。
ただ、提案の幅という点では…正直、今は打ち合わせに入る機会がそれほど多くないので、現場経験をすぐに提案に生かせているかと言うと、そこは少し理想とは違っているかもしれません。
S:総合職といっても、実際は人によって担当する仕事が違うんです。経験年数が長い人が社葬やお別れ会といった大規模な葬儀を担当したり、経験が浅い人は家族葬をメインで任されたりと、スキルに応じて役割が分かれています。
だから「大変でついていけない」ということはなく、段階を踏んで成長していける環境だと思っています。
入社時にはどのような研修を受けられましたか。
S:私が入社したとき、総合職で同じ時期に入った人はいなかったのですが、セレモニースタッフ(現在の準社員)として入社された方たちと一緒に研修を受けていました。
私は経験者ですが、研修内容が省略されることはなく、未経験の方と同じ研修プログラムでした。
ビジネスマナーなどの基本研修も含まれていたのですか。
S:はい。お辞儀の角度の練習など、いわゆる一般的なビジネスマナーも含まれていました。他にも葬儀に関する備品の名前や使い方、葬送儀礼の知識など、基礎からしっかり学ぶことができました。
研修の中で、特に印象に残っていることはありますか。
S:備品の呼び方が前職と全然違ったのが衝撃でしたね。例えば「経帷子(きょうかたびら)」という着物は、前職では「仏衣(ぶつい)」と呼んでいました。
他にも、公益社では使用しているけど前職では使っていなかった「点灯甜茶(てんとうてんちゃ)」といった備品があったり、式場設営の考え方も違っていたりと、最初は戸惑うことが多かったです。
 故人様にお着せする白い装束は「経帷子」「仏衣」など企業によって名称は様々。※画像はイメージです
他に、前職と比較して印象的だったことはありましたか。
故人様にお着せする白い装束は「経帷子」「仏衣」など企業によって名称は様々。※画像はイメージです
他に、前職と比較して印象的だったことはありましたか。
S:「故人様との距離感」も違うように感じました。
前職では社内に納棺師がいて、ご家族と一緒にお着替えをする“納棺式”を行っていたんです。
公益社ではエンバーミングを行うことでとても綺麗な状態でお帰りいただけるのですが、基本的にはご家族と一緒にお着替えすることは難しく、その点では少し距離を感じることがあります。
では、公益社の魅力はどんなところにありますか。
S:やっぱり会社が大きいというのは魅力だと思います。人数も多く、色々な人がいて、様々な経験をしている。先輩からの話を聞くだけでも学びになりますし、自分も続けていけば、多くの経験ができると思います。
実際に公益社に入社して、慣れるまでに苦労したことはありましたか。
S:最初は毎日出社する会館が違うというのが大変でした。前日にならないと翌日の出社場所が分からないので、「間違えたらどうしよう」という緊張感が常にありましたね。
今はある程度決まった会館への出社になってきたので、落ち着いています。
最後に、今後の目標を教えてください。
S: 5年間葬儀業務に携わると「葬祭ディレクター1級」の受験資格が得られるので、それは取りたいです。会社が業務時間内に研修をしてくれるので、それを受講して挑戦する予定です。こういった手厚い研修制度もとてもありがたいですね。
あとは、ご家族に寄り添えるディレクターであり続けたいというのが一番の目標です。
本日はありがとうございました。
【編集後記】 故人様にまつわる小さなエピソードを拾い、形にする。
日々の業務の中でSさんは、ご遺族の“想い”に寄り添うことを最も大切にしていました。
大きな組織でたくさんの経験を積みながらも、「距離感を大切にする家族葬の温かさ」に自らの適性を見出し、着実に歩みを進めるSさん。
彼女の目指す葬儀の形は、これからも、ますます深まっていくことを感じさせてくれました。
前職でも葬儀業界での経験があったSさんは、より広い経験を求めて公益社へ。現在は主に家族葬を担当し、ご遺族の想いに寄り添った“まごころ”の提案に力を注いでいます。
会社の共有文化や柔軟な社風にも支えられながら、自分らしいスタイルで成長を重ねてきたSさん。経験から気付けた自分の本音や今後の目標などを語ってくださいました。
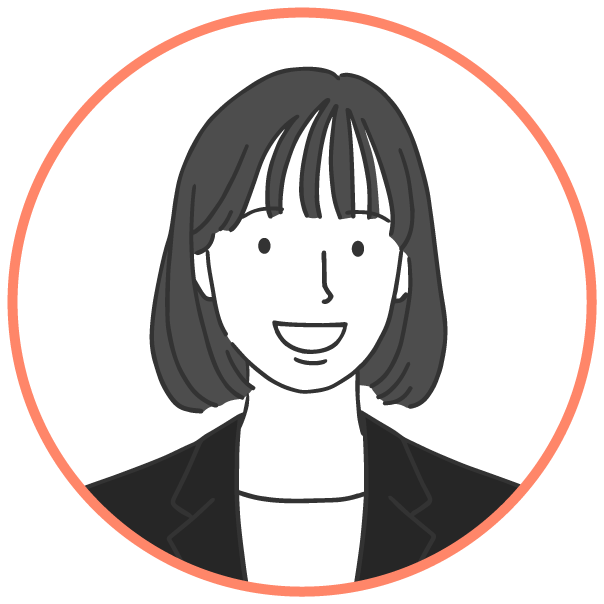
株式会社公益社
東京セレモニーサービス部 葬祭ディレクター:Sさん
大学卒業後、営業職や日本語教師などに従事。 その後、社会人経験を積んだ上で挑戦したいと考えていた葬祭業界へ転職。前職葬儀社にて約2年間、分業制の葬祭ディレクターとして勤務。 さらなるスキルアップや幅広い経験を重ねたいと考え、一貫担当制の葬祭ディレクターとして様々な現場に携われる公益社へ転職。
東京セレモニーサービス部 葬祭ディレクター:Sさん
大学卒業後、営業職や日本語教師などに従事。 その後、社会人経験を積んだ上で挑戦したいと考えていた葬祭業界へ転職。前職葬儀社にて約2年間、分業制の葬祭ディレクターとして勤務。 さらなるスキルアップや幅広い経験を重ねたいと考え、一貫担当制の葬祭ディレクターとして様々な現場に携われる公益社へ転職。
ご遺族の心に寄り添う。共有文化が支える「まごころ」のご提案。
本日はよろしくお願いします。Sさんが公益社に入社されて、1年ちょっとというところでしょうか。
S:そうですね。
現在はどのようなお仕事を担当されていますか。
S:今は葬儀の担当と、事前の打ち合わせを行っています。
ということは、すでに葬祭ディレクターとして一通りの業務を任されているということですね。
S:はい、そうです。
すごいですね。ちなみに、担当デビューされたのはいつ頃だったか覚えていますか。
S:入社して半年くらいだったと思います。
それは早い方でしょうか。
S:どうなんでしょう?
私は以前も葬儀会社に勤めていた経験がありましたが、研修は通常通りしっかり受けて、その後に担当になったという流れでした。
入社から半年で担当に就かれて、そこからさらに半年以上が経つわけですが、最近印象に残ったご葬儀などはありますか。
S:公益社では「まごころ枠」という取り組みがあって、故人様が思い入れのある物をご用意したり、好きだったものを葬儀で取り入れたりできるんです。
最近では、ハーゲンダッツのラムレーズン味が好きだったという方がいらっしゃって、ご家族からそのお話を伺ったので、葬儀当日にご用意させていただきました。ご家族にもとても喜んでいただいて、棺にも一緒に入れてくださいました。
 公益社から故人様へのプレゼント”まごころ枠”担当者が工夫し用意する。
公益社から故人様へのプレゼント”まごころ枠”担当者が工夫し用意する。
ケーキでゴルフ場を再現するとは…すごいアイディアですね!
S:はい(笑)。ゴルフボールやクラブは棺に入れられないこともあるので、どうにか形にできないかと工夫しました。
そういった“まごころ枠”のアイディアは、ご遺族の方からリクエストされるわけではなく、公益社さん側からのご提案なんですか。
S:そうですね。スタッフがそれぞれ打ち合わせの中で、ご遺族からお話を伺いながら、「何かできることはないか」と考えて準備をしています。葬儀当日に担当が変わることもあるので、打ち合わせ担当者からの引き継ぎも大切です。
先ほどのゴルフのケーキのように、先輩が過去の事例を教えてくれることも多いですし、良い取り組みは共有する文化があります。
やはり、公益社はスタッフの人数も多いので、それだけ色々なアイディアが集まりやすく、さらにそれを共有する仕組みがあるのも大きいですね。
その「共有の仕組み」は、具体的にどのようなものでしょうか。
S:データベース化されていて、写真付きで「こんな故人様だったので、こういう物をご用意しました」と記録されています。
それは貴重な情報ですね。リピーターのお客様がいらっしゃった場合にも、前回の情報を踏まえてご提案ができそうですね。
S:はい。全てのケースで写真が残っているわけではないのですが、データ上に「まごころ枠」という欄があって、そこに内容が記載されていれば、ある程度はイメージができますね。
本当に“想いを届ける仕事”という印象を受けました。ありがとうございます。
エンバーミングの効果と役割を伝える。柔軟なご提案を心がけ。
今のお話だと、ご担当されているのは家族葬が中心という印象を受けたのですが、実際はいかがでしょうか。S:今のところはあまり大きな葬儀は担当していなくて、基本的に家族葬が多いです。
公益社さんは大手ですから、大規模な葬儀のノウハウも豊富にあるかと思います。将来的に大きな葬儀にもチャレンジしてみたいという気持ちはありますか。
S:先輩が担当した大きな葬儀に入ったことはありますが、実際に見て「ちゃんと対応ができてすごいな」と思う反面、ご家族との距離感を大切にできる家族葬のほうが、自分には合っているかなと思っています。
以前は、もっと規模の大きな葬儀にも携わりたい気持ちが強かったのですが、今はお話をじっくり伺えたり、故人様のことを深く知れたりする家族葬に魅力を感じています。
公益社さんでは売上目標なども設定されていると思いますが、その点についてプレッシャーを感じることはありますか。
S:私は今、プランナーというより施行側なので、営業というほどではなく、金額的な部分にそこまで関わっていないんです。
ですから、正直プレッシャーはあまり感じていなくて…本当は感じなきゃいけないのかもしれませんけど。
でも、そのバランスが公益社さんらしいというか。会社からガツガツ言われるのではなく、それぞれの得意分野を生かす社風なんですね。
S:そうですね。売上やオプションの獲得率などのランキング表は共有されますが、スタッフそれぞれで受け取り方も違いますし、頑張り方も違うと思います。
エンバーミングについては、会社としても推奨している施術だと伺いました。実際にご提案される場面では、どんなお話をされているのでしょうか。
S:エンバーミングは自社の用賀会館で対応ができますので、可能な限りご提案をするようにしています。
最近は火葬までの日数が空いてしまうことも多いので、そういった場合には「ぜひエンバーミングを」とお勧めしやすいです。ただ、日程が短いと必要性を感じにくいこともあるので、そのあたりは状況を見ながら臨機応変にご提案することを心掛けています。
状況次第でご提案の仕方も柔軟に変えられているんですね。
S:はい。例えば、亡くなられた後にお口が開いてしまうこともあるのですが、エンバーミングを行うことでそれを整えることができます、というようなご説明もしますし、「亡くなってもきれいな姿を維持したい」という思いに応えるときにも、エンバーミングをお勧めします。
「やっぱり家族葬が好き」転職後に気づいた本音。
Sさんはいつも用賀の会館に出社されているのでしょうか。S:いえ、2024年の10月からは日吉会館の所属になっています。ですから日吉への出社が比較的多いですが、その日によって出社先は変わります。
用賀会館と日吉会館では、雰囲気などに違いはありますか。
S:用賀会館はスタッフがたくさんいて、皆さん忙しそうなんですよ。だからちょっと話しかけづらい雰囲気があるかもしれません(笑)。
一方で、日吉会館はアットホームな感じがあって、社歴が長い方も多いので、いろんなお話が聞けるのが良いなと思っています。
それは素敵な環境ですね。
少し話題が変わりますが、今回の転職活動は葬祭ジョブでサポートさせていただきました。当時、複数の求人をご案内した中で、最終的に公益社を選ばれた理由をお伺いしてもよろしいですか。
S:一番の理由は「大きな会社だから」という点です。前職では少人数の体制で家族葬ばかりだったので、もう少し大きな規模の葬儀も見てみたいな、という気持ちがあって決めました。
実際には、現在も家族葬が中心とのことですが(笑)
S:そうなんですよ(笑)。
でも今は先ほども話した通り、逆に「やっぱり家族葬がいいな」と思えているので、結果的に自分に合ったスタイルが見えてきた気がします。
転職して大変だったことや、葬祭ジョブへの要望などはありましたか。
S:特に大変だったことや不満はなかったですね。サポートもしっかりしていただいたと思っています。
転職前に「現場での経験を通じて提案の幅を広げたい」と話されていたかと思いますが、実際に公益社に入社してから実現できた点、また変化を感じた点はありますか。
S:働き方としては、前よりも残業時間がかなり減って、早く帰れる日が増えたというのはすごく大きいです。これは本当にありがたいですね。
ただ、提案の幅という点では…正直、今は打ち合わせに入る機会がそれほど多くないので、現場経験をすぐに提案に生かせているかと言うと、そこは少し理想とは違っているかもしれません。
目指すは“寄り添えるディレクター”ブレない想いと今後の目標。
公益社には「地域限定社員」と「総合職」という2つの職種がありますが、Sさんは最初、総合職に対して少し不安もあったと伺いました。実際に働いてみて、ギャップなどはありましたか。S:総合職といっても、実際は人によって担当する仕事が違うんです。経験年数が長い人が社葬やお別れ会といった大規模な葬儀を担当したり、経験が浅い人は家族葬をメインで任されたりと、スキルに応じて役割が分かれています。
だから「大変でついていけない」ということはなく、段階を踏んで成長していける環境だと思っています。
入社時にはどのような研修を受けられましたか。
S:私が入社したとき、総合職で同じ時期に入った人はいなかったのですが、セレモニースタッフ(現在の準社員)として入社された方たちと一緒に研修を受けていました。
私は経験者ですが、研修内容が省略されることはなく、未経験の方と同じ研修プログラムでした。
ビジネスマナーなどの基本研修も含まれていたのですか。
S:はい。お辞儀の角度の練習など、いわゆる一般的なビジネスマナーも含まれていました。他にも葬儀に関する備品の名前や使い方、葬送儀礼の知識など、基礎からしっかり学ぶことができました。
研修の中で、特に印象に残っていることはありますか。
S:備品の呼び方が前職と全然違ったのが衝撃でしたね。例えば「経帷子(きょうかたびら)」という着物は、前職では「仏衣(ぶつい)」と呼んでいました。
他にも、公益社では使用しているけど前職では使っていなかった「点灯甜茶(てんとうてんちゃ)」といった備品があったり、式場設営の考え方も違っていたりと、最初は戸惑うことが多かったです。
 故人様にお着せする白い装束は「経帷子」「仏衣」など企業によって名称は様々。※画像はイメージです
故人様にお着せする白い装束は「経帷子」「仏衣」など企業によって名称は様々。※画像はイメージです
S:「故人様との距離感」も違うように感じました。
前職では社内に納棺師がいて、ご家族と一緒にお着替えをする“納棺式”を行っていたんです。
公益社ではエンバーミングを行うことでとても綺麗な状態でお帰りいただけるのですが、基本的にはご家族と一緒にお着替えすることは難しく、その点では少し距離を感じることがあります。
では、公益社の魅力はどんなところにありますか。
S:やっぱり会社が大きいというのは魅力だと思います。人数も多く、色々な人がいて、様々な経験をしている。先輩からの話を聞くだけでも学びになりますし、自分も続けていけば、多くの経験ができると思います。
実際に公益社に入社して、慣れるまでに苦労したことはありましたか。
S:最初は毎日出社する会館が違うというのが大変でした。前日にならないと翌日の出社場所が分からないので、「間違えたらどうしよう」という緊張感が常にありましたね。
今はある程度決まった会館への出社になってきたので、落ち着いています。
最後に、今後の目標を教えてください。
S: 5年間葬儀業務に携わると「葬祭ディレクター1級」の受験資格が得られるので、それは取りたいです。会社が業務時間内に研修をしてくれるので、それを受講して挑戦する予定です。こういった手厚い研修制度もとてもありがたいですね。
あとは、ご家族に寄り添えるディレクターであり続けたいというのが一番の目標です。
本日はありがとうございました。
【編集後記】 故人様にまつわる小さなエピソードを拾い、形にする。
日々の業務の中でSさんは、ご遺族の“想い”に寄り添うことを最も大切にしていました。
大きな組織でたくさんの経験を積みながらも、「距離感を大切にする家族葬の温かさ」に自らの適性を見出し、着実に歩みを進めるSさん。
彼女の目指す葬儀の形は、これからも、ますます深まっていくことを感じさせてくれました。
燦ホールディングス株式会社/株式会社公益社様の企業情報
■残業 30時間
■平均年齢 49.2歳
■産休、育休実績の有無 産休・育休実績、復帰実績ともに有り